みなさん「サングリア」って知ってますか?
実は「サングリア」って、家庭では作れないことになっているのです。
理由は「その行為によってアルコール度数が上がってしまう可能性があるから」というのが根拠です。
ですが、納得がいかないので浦和税務署に電話に問い合わせました。
(以下会話文はすべて意訳)
僕「一般的に発酵が起こりにくい冷蔵環境においてワインに果物を漬け込み、その前後において簡易的なアルコール度数計を用いて、アルコール度数の1%以上の上昇が無いことを確認した場合に飲用し、それ以上上昇した場合は不可飲処置をして廃棄する場合でもダメですか?」
と聞いたところ回答としては
浦和税務署「ダメです。そもそも、飲用の直前である場合を除き、酒に他の物質を混和することは、例外を除き禁止されています」
との回答でした。なので、僕はこれについて
僕「であるならば、酒税相当の税が掛かっている実験用アルコールに、クエン酸を混和させて放置することは違法なのか? そもそも、酒税法は適切な納税を行わせるための法令であって、脱税を禁止させる根拠にはなるが、上記の通り脱税しないよう工夫している行為まで禁止することは妥当ではないし、もし徴税の観点が重要なのであれば免許制度を見直すべき」
と話したところ、税務署は折り返して連絡するとのことになりました。
しかし、個人的に酒税法について思うことは多々あったのと、この件をTwitterに紹介したところ、様々な酒税法に関する疑問が寄せられたので、それをまとめて浦和税務署に再度電話して伝えたところ、項目が多すぎるので書面で見たいとの返答がありました……が、税務署や警察署は質問を本来は紙で受け取ることはしていないので、別の方法を考えることとなりました。
そして、たまたま直近で浦和に行く用事があったので、そのほかの項目もまとめて文書にして、持参することにしました。
当日はノーアポで持参したのですが、2名の酒税担当者の方とブースでお話することとなり、持ち込んだ書類については「相手方がコピーする」という方法をとることにより、相手方で見ることができるようにしました(※この方法は私が川口警察署から教わって、私が税務署に教えました)。
そして1~2時間ほど、質問に関する用語や意図についてお話をしまして、
浦和税務署「様々な問題に関連しているため、回答にはかなり時間がかかると思うが、確かに回答する。回答方法は(制度上)書面は交付できないが、対面であったり、どうにかちゃんと示せるような方法を工夫したい」(意訳)
とのご返答をいただきました。
また、質問項目の殆どについて、過去に見当されたこともないとおっしゃっていました。
(例えば、そもそも燃料や消毒液を飲むことは想定していないし、不可飲処置は、国税庁が風味などを元に考えているが、毒物を混入させたケースは想定していないとのこと)
しかし、その後、税務署との会話の中で疑問に思われた点も含めて、質問用紙を改めて見直すと、イケてない点も多数あったため修正をした後、印刷をして返信用封筒を同封して浦和税務署に送付することにしました(こうすれば受け取ってないことになるため)。
送付した質問用紙
今後は、浦和税務署はこの質問(大問は全19問だが、小問は条件分岐により200問程度あるはず)に従って、上級官庁(国税局・国税庁など)と協力して回答を考えると思われますが、とはいえ、この質問は「アルコール事業税(経産省)」「揮発油税(国税庁)」「食品衛生法(厚労省)」「薬機法(厚労省)」「バイオエタノールの取り扱い(資源エネルギー庁)」、さらには習俗(文化庁?)やバイオテクノロジー(文科省?)の話などの多方面に係わる問題であるため、他省庁との調整など、相当な時間はかかるだろうと思われます。
とはいえ、そもそもの「酒税」というものは、本来は適切な納税のための制度であって、酒造りを統制するためのものではあってはならないはずです。質問用紙にも書いたのですが、現行憲法であれば、本来は適切な納税制度が先にあるべきで、これについての脱税行為を罰するようにすべきだろうと思われますが、おそらくそうではない明治憲法下の制度が残存していることによる不合理だと思われます。
そもそもの問題は、国税庁をはじめとして不備のある法律を放置したことによるのですが、……しかし問い合わせ先としては現場にするしかないため、現場の人も可哀想です(ただ、国民はそれ以上に困っている)。
質問は多岐にわたっていますが、これは役所を困らせるための行為というよりもむしろ、このような諸々のケース、あるいは脱法的な酒造りの方法があり得ることを指摘しており、それはむしろ健康に有害なことを助長すること(例えば酒税法が原因で、ワインに消毒液を混和してからサングリアを作ればよいのか? ワインに毒を入れたらサングリアを作れるのか?)の指摘であって、本来は国は国民の生活向上を目指すべきであって、やはり望ましくはないわけです。
なので、私はいわゆる社会活動家のようなデモであったり、ロビイング活動についてはあまり期待していないですし、さらに言えば国会議員についても、国民のために古い法律を改正しようという奇特な人も殆どいないだろうと思うところで、そのため、私が発見した公証人による合法性確認ができることを前提に、税務署に問い合わせることとしました。
結果が出るには相当程度かかると思いますが、個人的には、こんな下らない質問に真面目に答えるよりは、制度を改正してしまったほうが、よほど処理が楽だと思います。
なお、税務署の職員さんは非常に穏和かつ真面目な方で、こちらにもすごく丁寧に接してくださいましたので、しっかりと取り組んでくださると確信しております。
つまり、市民が行政に意見を言うにしても、ちゃんとした方法で、お役所側の都合にも理解を示しつつ、法律に則り、かつ変に偏った思想などに基づくわけではなく、法律などの合理的な根拠に基づいて、問題点をクリアにして意見・主張することが大事ということです。
あしやま
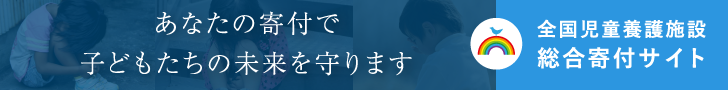




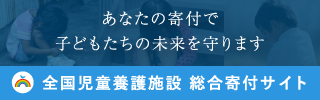





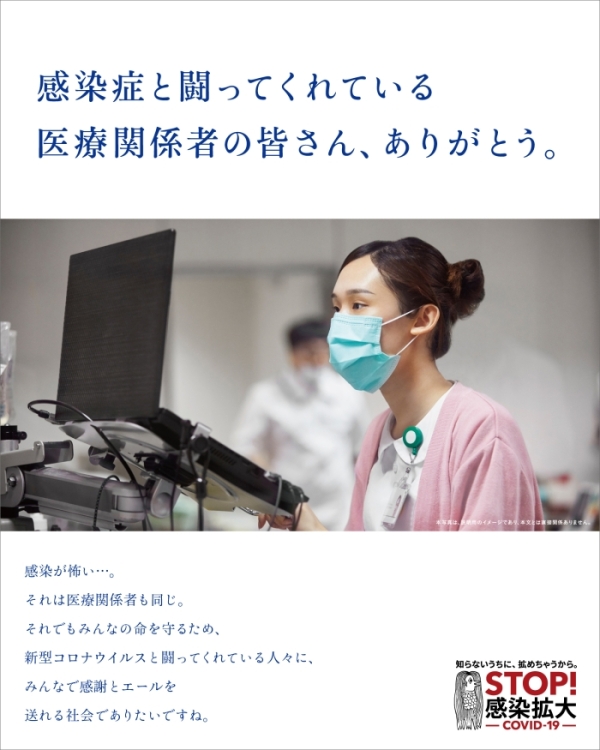

0 コメント