みなさまこんにちは、あしやまひろこです。
令和6年3月27日に、わいせつ図版に関する文書を、川口公証役場に私署証書の認証を嘱託して、拒否を受けて理由書を交付された件及び、令和6年5月31日に、弁護士法に関する文書を、同じく川口公証役場に私署証書の認証を嘱託して、公証を受けたものについて、弁護士を中心に多数のご意見を頂戴していますので、改めてこちらに見解を簡単に述べておきたいと思います。
当初私もどういう効果があるか?についてあやふやな部分もあったのですが、実際に行為を行ってみて、またTwitter上で弁護士を中心に様々なツッコミを受ける中で精緻化しましたので、これまでTwitterで断片的に述べてきたことを簡単にまとめました。
1.適法性の確認はできないが推認は得られることについて
当初私は「適法性の確認ができる」ような旨のことを伝えていましたが、これは簡単のためにそう記載したのであって、正確には「違法・無効でないことが推認される」またこの反対解釈から「適法であることが推認される」という記述が正しいため、訂正します。
理由として、公証人法26条より、公証人は違法・無効の行為について公証をすることが不可能であり、結果的に公証を受けた文書は、違法・無効でないことが審査されるためです。
もちろん公証人は「違法・無効」でないことのみを審査しているのであって、「適法性」の審査は全く行っていませんが、公証は「違法・無効」でないことの審査を行うため、反対解釈として「適法性」の推認が当然に生じます。
したがって、公証役場や公証人に対して「適法性」の確認をしてほしい、などのように依頼することや、得られた結果をもって「適法」や「合法」が「確定」したと述べるのは避けましょう。あくまでも、書かれた文書の記載内容について「適法」や「合法」の「推認」が得られた、という話になります。
また、本当に違法・無効でないか、あるいは合法なのか、は実際に行為を行ったあと、(事件性があれば)裁判によって確定されることになっています。これは、どのような種類の行政文書であったとしても、後の裁判で覆されることがあるのと同じです。
法哲学的には、論理的にあらゆる事柄は事前に違法・無効か否かは判断がつかなければおかしいのですが、人間の判断能力は完璧ではなく、さらに現実社会では様々な要因によってどうなるか分からないため、事後的な判断として裁判がなされいるわけです。しかし、裁判も間違いがあるから3審制を設けているのであって、最高裁判決も必ずしも真理とは限らず、便宜的にそれを多くの人が信用しているだけにすぎません。
ですからもちろん、実際の行為は、文書に記載されていない要因によって違法・無効となる可能性は十分にありますし、公証人の判断がそもそも間違っていることもありますが、公証が無効となるまでは、後述の理由も含めて推認が生じて、文書の存在による効果が生じます。
2.公証人の判断の権能について
弁護士からは、公証人に適法性を判断する権能がないという意見も多数寄せられましたが、公証人法26条にある通り、違法・無効を判断する義務が法律によって課せられていることから、結果的に適法性の判断の権能も有すると考えられます。
ただ、業務として行っているのはあくまでも「違法・無効」でないことの判断です。
3.公証人の判断の義務の範囲について
少なくない弁護士が、公証人の判断の義務が薄弱であるから、効力がないと主張していました。
しかし、そもそも公証人は法律上は、違法・無効の文書を認証してはならない義務があります。このなかで、もしも違法・無効な認証してしまった時の、公証人側の公証人法26条そのものへの違反や、善管注意義務違反、虚偽公文書作成罪等の範疇を示すものとして、平成9年9月4日の最高裁判決において、審査すべき義務を負う範囲が示されています。これは、公証人が責任を負うべき範疇を決めたものであって、公証の嘱託者側の認識に影響を与えるものではありません。同様のことは、一般的な公務にも言えることです。
もし公証人も含めた公務員の善管注意義務の範囲が定められていることを以て、その発行する書面の有効性がないなどと言ってしまったら、裁判の判決、捜査令状、その他一般の行政が発行する書面すべてについて、信憑性がないのだから信ずるな、という話になります。
つまり、公務員に課せられた義務や実際の公務員の判断と、書面の効力は別の話ということです。
なお、審査の能力が限定されているからといっていい加減な審査をしてもよいことはまったくなく、法令に記された通りに、読み取れる範囲で審査する義務があることについては、日本公証人連合会が編集した『新訂 公証人法』(2012年)でも『公証人法』(2004年)でも当然に記されています。
4.公証を与えられた文書の刑法・刑訴法上の効力について
公証された文書は上記1の通り、その文書が無効とされるまでの間は、書かれた内容は違法・無効でないことが推認されます。したがって、平成元年7月18日の公衆浴場法違反事件などに示される通り、その書面に記載された行為をして、あとからその行為が違法と司法によって判断されたとしても、犯罪に関する故意が成立しません。
つまり公文書という間違ってはならない性質の文書は、仮に実際の担当者が間違って作成したとしても、市民からすれば信用に値する文書であるということです。
公衆浴場法違反事件では、地方議員や、地方行政の一般の公務員の判断などがその理由となっていましたが、公証人の場合、法秩序の維持と国民の権利の保全を使命とする法務省が管轄し、法務大臣の下で予防司法の公務を行う特別な公務員が、法令に従って違法・無効でないことを審査するものであるため、公衆浴場法違反事件で故意が成立しないのならば、公証人による公証でも、当然に故意が成立しないと思われます。
学説としても、松原久利の『違法性の錯誤と違法性の意識の可能性』において、「自己の行為を適法とする公の情報を信頼して、自己の行為は適法であると信じた場合には違法性の意識の可能性はない」(79頁)、「当該行為が予見可能な段階で、照会等の適切な手段により行為は適法であるとの信頼に値する情報が得られた場合は、違法性の意識の可能性はないというべきであろう」(123頁)といったものがあります。
なお、判例データベースを簡単に探しても、公証実施のシチュエーションによる無効(立会人の不適格)や、隠れたる事情によって実際に起きた行為が無効(当事者が認知症だったり、別の利息が適用される商行為だったため、実際の行為に限って無効)、は見つけられましたが、書かれた書面そのものが無効と判断されたケースは、調べた限り見当たりませんでした。
加えて、昭和37年3月1日最高裁判決の通り、刑事事件において、公証の過程に瑕疵があっても公証された文書は真正に成立していると示されており、かつ刑訴法323条においては公正証書その他公務員がその職務上証明することができる事実について公務員の作成した書面が証拠とできるとあることから、公証された文書は、刑事事件における故意を棄却させるための推認を与える効果があることがわかります。
これは刑事事件において警察が捜査令状に基づき捜査を行った際に、あとから捜査令状の発行の根拠が間違っていて令状が無効となっても、無効となる前の捜査令状に基づいて捜査を行った警察官に犯罪の故意や責任が生じないのと同じです。
なお、民法上の責任は別途生じることがあります。
5.公証の基準について
実際に自身が認証を嘱託した状況、また周囲からの情報によれば、公証人は公正中立に、極めて保守的な判断をします。それは、公証人は司法ではなく行政に属するため、違法とも合法とも判断つかないものについて、法令違反の可能性があるなかで、あえて権利を拡張するような判断をするような性質を持たないためだと思われます。
したがって、違法とも合法とも判断つかない場合は、いったん拒絶を行い、異議申立があった場合は、その後の判断は法務局長、法務大臣に委ねられることになりますが、ここも法の執行機関である行政であるため保守的な判断を行うようです。
したがって、どちらとも判断が全くつかないような場合は、一応拒絶を行い、司法に判断を委ねている、というのが実情のようです。
6.公証拒絶の場合の効果
公証が拒絶された場合は、未然の行為につき「違法・無効」であることの推認を得ることができます。これは、従来一般的に、当該行為が刑法・特別刑法上で違法であるか否かについては、刑事事件化することを待たねばならなかったところ、行為が発生するよりも前に行政に判断を仰ぐことが可能であることを示します。
公証の成立および拒絶については、法務局長および法務大臣に対する異議申立が可能であり、さらに通常裁判も可能となるため、未然の行為について、その違法・無効の推認または違法・無効でないことの推認について、文書の成立または不成立を事件として、その判断および当然に発生する推認の正しさについて争うことが可能です。したがって国を相手取って、準抽象的違憲審査とでもいうべき、違憲訴訟を実施することも可能です。
これは参考意見しか交付されない、対象となる法令が限られている法令適用事前確認手続や、規制について規定する法令の解釈及び当該法令の適用の有無を確認できるグレーゾーン解消制度とは全く異なるものです。
この制度は法律作成の際に参考となったドイツ法とも異なっており、明治41年(1908年)に成立し、昭和24年(1949)年には施行規則にて手続きがより明確化されていたにも関わらず、従来ほとんど使われていなかったらしいことには、一種の驚きを感じます。
6.その他参考情報
当初手続きを間違えて法務局にて別の手続きをしたところ、公証人に当該確認を行うということを法務省職員と話していた際に、職員の個人的な立ち話として、このような公証の使い方は前代未聞で、抽象的違憲訴訟が成立してしまうことや、公証が成立した場合は、警察・検察・裁判所は公証を斟酌するだろう、といった話を聞きました。
また、全くの別件で警察署に用があったさい、司法警察員にこの件を話したところ、それは警察において捜査令状の発行を受けて捜査を実施するのと同じ理屈が働き、またそもそも公文書に従った行為には故意が成立しない、という旨の見解を聞きました。なお、警察の一般的見解を警察官向けの教科書(執筆は検察官)を読んで確認しましたが、おそらく同じだと思われます。
したがって、ここまで記述した考え、特に刑法・刑訴法上の効果については、おそらく警察を含めた行政側の意見とも合致するものであると思われます。
さらに付け加えて言うならば、行政の行う審査や許認可は、多くの場合はその行為が法令に定める形式に該当するか、すなわち違法・無効の有無を審査しているものであって、許認可が下りるというのは合法性が担保されるというよりもむしろ、行政から違法・無効でないことを審査されたとも言えるのではないでしょうか。規制産業における実務としても、弁護士確認などをするよりも先に、監督官庁に問い合わせて見解を聞くというのは通常の話です。そう考えると、公証はあらゆる行為、あらゆる法令について審査するところが独特ですが、きわめて一般的な行政手続きの側面があるようにも思われます。
(2024年9月7日追記)
結局のところ「適法性は確認できるのか?」でいうと、厳密に言えば「適法性の推認が得られる」となりますが、その後に万が一「違法」と裁判で認定されても罪に問われない(故意が成立しない)のですから、実務上は「適法性の確認ができた」という理解でも問題ないように思います。また、仮に公証人が判断を誤って公証したとして、その誤判断は故意でないならば責任は問われないでしょう(間違った捜査令状を発行した裁判官が罪に問われないのと同じです)。なお、公証よりもあとに法改正があったり、類似の事件で新たに違法性が認定された場合や、ガイドラインの変更(法令の解釈の変更)があった場合は、過去の公証については意味を持たなくなる場合もあるかとは思います。また当然ですが、公証の内容を実行して違法が認定されたら、おそらくその公証はあとから取り消されるでしょうし、取り消されたあとは当然、違法性の認識の可能性があるため犯罪は成立するはずです。
本記事は、あしやまと、国立大学に勤務する刑法学者(博士)、公証制度に詳しい実業家が共同で研究して得た知見を、あしやまの立場でまとめたものです。
詳細については、最初に嘱託した公証に関する異議申立のプロセスがすべて完了した段階で、しかるべき場所にて明らかにします。
上記、何かご意見や相談のご依頼がある場合は、メールまたはTwitterまで連絡ください。
(2024年10月28日追記)
「どういう意味かもっと分かりやすく知りたい」「自分は●●で困ってるから相談したい」という声をいただき、すでに2件ご相談を受けて、実際に有償で対応してご好評をいただいたので、これにスポットをあてたサービスを出品しました。
https://coconala.com/services/3477082
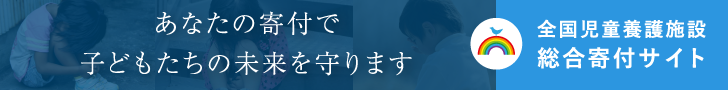

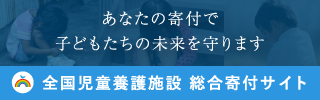







0 コメント